- 貧困は一人による解決が困難を極める、という前提を皆で共有しなければいけない。
- 貧困を脱するためには必ず誰かの支援が必要となる。
- 支援を悪用する輩はたくさんいるが、結局は書かれたシナリオのごとく淘汰されるので、良心に従った支援をすれば良い。
貧困についての本を読んだ
最近は仕事帰りの電車と自分タイムにこの本を3か月かけてチマチマ読んでいました。
読者は17歳を想定した構成でしたが、アラフォーな私でも貧困に対する解像度が上がる内容でした。
いろいろ考えさせられる内容であったと感じました。
平たく言うと、この本の主張は「貧困は困っている人(家族)を周りの支援で解決できる」です。
具体的には「自分が住んでいる地域が困っている家族を支援する」というやり方です。
ただ、今のご時世を鑑みるとそれ自体が難しいと感じる内容でもありました。
貧困は1人ではどうにもできないという前提
この本の主張は貧困を脱するためには周りから支援を受けることを必須としています。
逆に考えると、とてもむごい事実があります。
貧困はもはや一人ではどうにもできない、ということです。
貧困は誰かの助けなしでは解決できない、ということです。
支援って簡単にできるものなのか
私自身、誰かの支援はとても大事なものだと実感しています。
プライベートでも仕事でも、私が困ったときに周りから助けられたことは何度もありましたし、本当にありがたいことでした。
困ったときに助けてもらえる人がいるということは、私の人生にとって財産であり、幸せであることを実感させてくれます。
この本にも同じことが書かれていました。
ただ、正直なところ、昨今の状況を鑑みると人を支援するということは簡単にできるものなのか、と感じています。
私は非常に難しいと考えます。
というもの、誰かを支援するというのは、支援するためのいろいろな条件を満たす必要があると感じたからです。
この本は身近な人、1人で良いと言っているのですが、それでもいろいろな壁をクリアしないといけません。
支援の条件
身近な人、1人を支援するだけでも困難を極めると考えます。
私は専門家ではないので初心者な発想ですが、具体的には次の通りです。
- お互いが倫理的な対応をする必要がある
- 支援を行う側は一方的に支援をする覚悟が必要である
詳細を述べると文章が冗長になってしまため割愛しますが、これって個人でできることなのでしょうか。
支援とは慣れてしまえば依存となり、当たり前に変わります。
当たり前になると人は感謝の気持をなくします。
なぜか助けられる立場の人が傍若無人な態度をとる事態になるのです。
貧困は1人で脱することができないことと同様に、支援も1人ではできないと思わざるを得ません。
支援を悪用する輩
もう一つ懸念があります。支援を悪用しようとする輩の存在です。
支援を悪用する輩は良心が欠如している輩といってもいいでしょう。
言い換えれば、嘘つきな輩といえるでしょう。
虚偽の申請、二重申請、助成金目当てに嘘の会社を設立、身分や職業の偽装、資産申告の不正やら、挙げれば枚挙にいとまがありません。
輩に対していろいろな言葉を浴びせることはできますが、ひとつ言えるのは、必要な支援を受けるべき人たちが受けられないことです。
では、私が個人でできうる対策はあるのでしょうか。
まぁないわけです。
仮に、支援をする相手が支援を悪用する輩であることを見破れなかったら、私の気持ちはどう処理すればいいんでしょうかね、となるわけです。
良心を基準にしたい
だからと言って悲観する必要はないと考えます。
なんていいますか、噓つきは嘘つきなりの終わり方をするからです。
まるで嘘をやった程度の分だけ、反動でそれなりの終わり方をする。
書かれたシナリオのようです。
演技のようですね。
ただ、自分の意識の範疇でみてみれば悪人繁盛であるわけですが、もっともっと長い目で見れば成敗される運命にいくものだと思います。
思います、ですので保障なんてあったもんじゃありませんが、それでもなぜか勧善懲悪はあるものだと感じるわけです。不思議なことに。
このことから、支援を受ける側は良心を持った人しか支援を受けられないのです。
なので、支援を悪用する輩のことは気にすることはないのだと感じます。
支援を悪用する輩を考えるよりも、自分がしたい支援を考えるべきなんじゃないかなと感じます。
結局は良心を基準にすればよいと思います。
そう考えると、支援とは、お互いが良心に従ったとても高尚な取り組みなのだと思います。
貧困は解決策がある。支援をすることでのみ達成される。
支援をする側・受ける側、双方に良心を前提とする。
何とも因果なことだと思います。

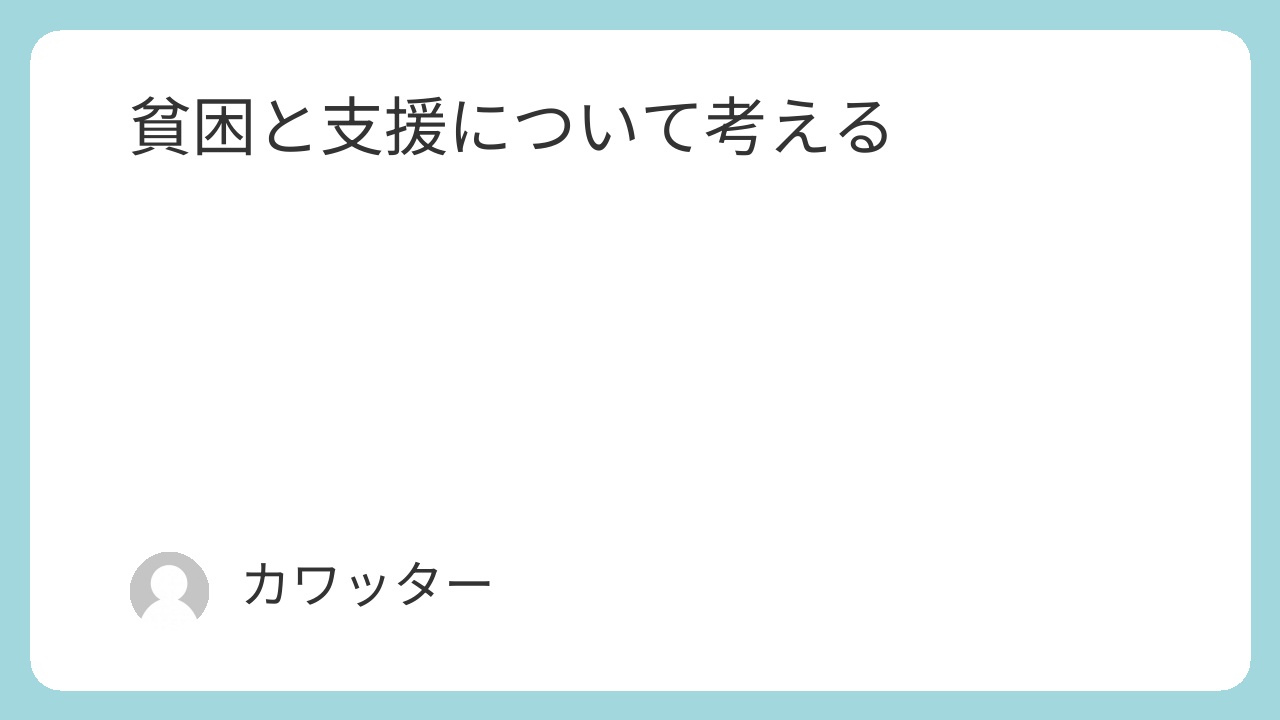
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b792850.ad7d0941.1b792851.bfdd1440/?me_id=1213310&item_id=20764349&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9634%2F9784167919634_1_5.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


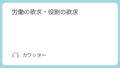
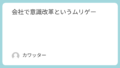
コメント スパム対応をしたつもり、コメントは残す方向で頑張ってます