世はDX時代です。弊社もトップダウンでDXをやれという指示が降りて以降、現場サイドの我々も否応なしにデジタルと向き合う日々になりました。
それに伴い、私は生産技術時代のときから、製造業の現場で働く職人たちと向き合うたび、彼らがITを拒む姿勢に頭を悩ませてきました。
実感はベテランであるほどITを拒む傾向が強いです。天ぷらでしょうか。いいえ、テンプレです。
もちろん全員ではありません。
私自身、この記事をアップした時点で設備屋を1年して区切りであること、一応私はIT企業勤めであることから「なぜなのか」を考えてみることにしました。
↓生産技術時代のまとめ↓


- 職人はベテランであるほど今の仕事を「すべて」体にしみこませたから、それ以上の新しいことは体に入れられない
- ITと職人は共生できる
IT vs 職人な優劣をつけるよりも、お互いの足りない部分を補完し合うことを目指すべき
目次です
今の仕事を「すべて」体にしみこませたから
製造業の職人がITを拒む最大の理由は、彼らが何十年もの経験を通じて「今の仕事」を体に染み込ませてしまったからだと考えています。
新しいツールやシステムを導入しようとしても、彼らの頭と体はすでに「これまでのやり方」で完全に埋まってしまっているのです。
「おれはこのやり方が一番あってるんだ」超ベテランの職人が言う理由もここにあると考えます。
裏返して考えてみると、職人の記憶の全リソースを費やしたことと同義といえるでしょう。
そのため、他の新しいやり方を入れるだけの余裕がないのと同じなんじゃないかと考えます。
体が勝手に動くまで刷り込ませた「今の」業務に対しそれ以外の方法は一切取り入れることはできないということになります。
悪い解釈をするならば、容量(メモリ)のムダ使い♥となるわけです。

冨樫 義博, HUNTER×HUNTER, 集英社, 54話
職人の名誉のために補足しますが、職人は融通が利かないだけで、まったくITに負けてません。
私が極論いいたかったがために出したヒソカです。
話を戻します。
もし、職人に対し、一部だけ今までと異なるやりかたを導入したとしましょう。
今までやってきた手順が一つ違うだけでも、職人にとってはたった一つ導入したやり方を”感覚で”強く意識することになるため、体が勝手に動くことはなくなるわけです。
結果、職人は「今のやり方がよい」という結論づけるのではないか、というわけです。
やり方をかたくなに変えない職人、話を聞かない職人
現場でよく見かけるのは、新しい提案を持ちかけても「そんなものは必要ない」と一蹴する職人たちです。
例えば、私が設備のメンテナンス効率を上げるためにタブレットを使った記録システムを提案したとき、あるベテラン職人は「紙とペンで十分だ」と言い放ち、それ以上話を聞いてくれませんでした。
この頑なさは、単に新しいものへの抵抗感というより、彼らにとって「変えること自体がリスク」に感じられるからではないかと思います。
実際、製造業ではミスが大きな損失につながるため、「これまでうまくいった方法」を守る姿勢が根強いです。
何十年にも研磨された、うまくいったカンコツの積み重ね
職人たちがITを拒む背景には、彼らが何十年もかけて磨き上げた「カンコツ」があります。
例えば、旋盤加工の職人が「音と振動で切削具合を判断する」といった技術は、データやセンサーで値を取ることまでは簡単でも、職人と同じように値を解釈することは難しいです。
このような「体で覚えた技術(5感の観点でいえば技能)」は、数値化できない感覚的な領域に依存しており、ITツールがそれを再現するのは難しいといえます。
職人はこのカンコツで「自分そのもの」であるセンサーから「今まで積み重ねた傾向と対策」をひねり出しています。
超高感度な異常検知および予兆検知を実現している事実は見過ごせないものです。


変えようとしても変わらない、なぜなら何十年もかけて体に染みつかせた手順だから
では、IT導入を試みても、職人たちの行動が変わらないのはなぜでしょう。
それは、彼らが何十年もかけて体に染み込ませた手順が、もはや「考える」レベルを超えて「反射」の領域に達しているからです。
「反射」の領域は心理学でいう「学習と強化」に属するものです。
習慣化された行動は、新しい選択肢があっても無意識に古いパターンに戻ってしまうことがわかっています。あれこれって機械学習の過学習とおなじじゃね?
例えば、私が現場でデジタル計測器を導入したとき、職人は「使い方がわからん」から「使いづらい」と言いながら、結局慣れたアナログゲージに戻ってしまいました。
※もちろん「ここはよくなったが、ここがダメになった、トータルで悪くなった」と具体的に指摘をいただける職人もいます。
職人にとって、ITは「頭で理解するもの」ではなく、「体で覚え直すもの」です。
「体で覚え直すもの」となれば、その理解はハードルがあまりにも高いものです。
わたしだってITを体で覚えたかと言えばそうではないですし。
職人の覚えるメモリは要領MAX、もう入らない
結局、職人がITを拒むのは、彼らの「覚えるメモリ」がすでに満タンになったんだと考えます。
何十年もかけて築いた知識と技術で頭がいっぱいになり、新しい情報を入れる余裕がないのです。
これは、パソコンのハードディスクがいっぱいになると新しいファイルを保存できない状況です。
既存のファイル(覚えたこと)はロックされてしまい、上書き保存ができないようなものです。
なすすべ無しか?いやそうじゃない
いろいろ職人がITを拒むことを偉そうに述べましたが、私自身、なすすべ無しかとまでは思いません。
むしろ、職人とITは共生できます。
ここは言い切れます。
彼らの容量(メモリ)を上書きするのではなく、今のやり方を尊重しつつ、少しずつ「拡張」していくアプローチを行います。
例えば、ITを「補助ツール」として位置づけます。
彼らのカンコツを活かせる形で提案します。
依然として費用対効果の壁は残りますが、現場での抵抗を減らす一歩になるでしょう。
ITと職人、どちらが良いか優劣をつけることはするべきではありません。
お互いの足りないところを補完し合うべきです。
そんな共存関係が、本当の意味でのデジタルによる変革となると強く感じています。
私はDXによる変革が古い仕組みや組織を新しく変えることではなく、人の意識を前向きなものに変わらせるものと考えます。
前向きな意識の実感は本当の意味でのDX(Digitalを手段とした人の意識のTransformation)となると、私は信じています。


変更履歴
記事UP

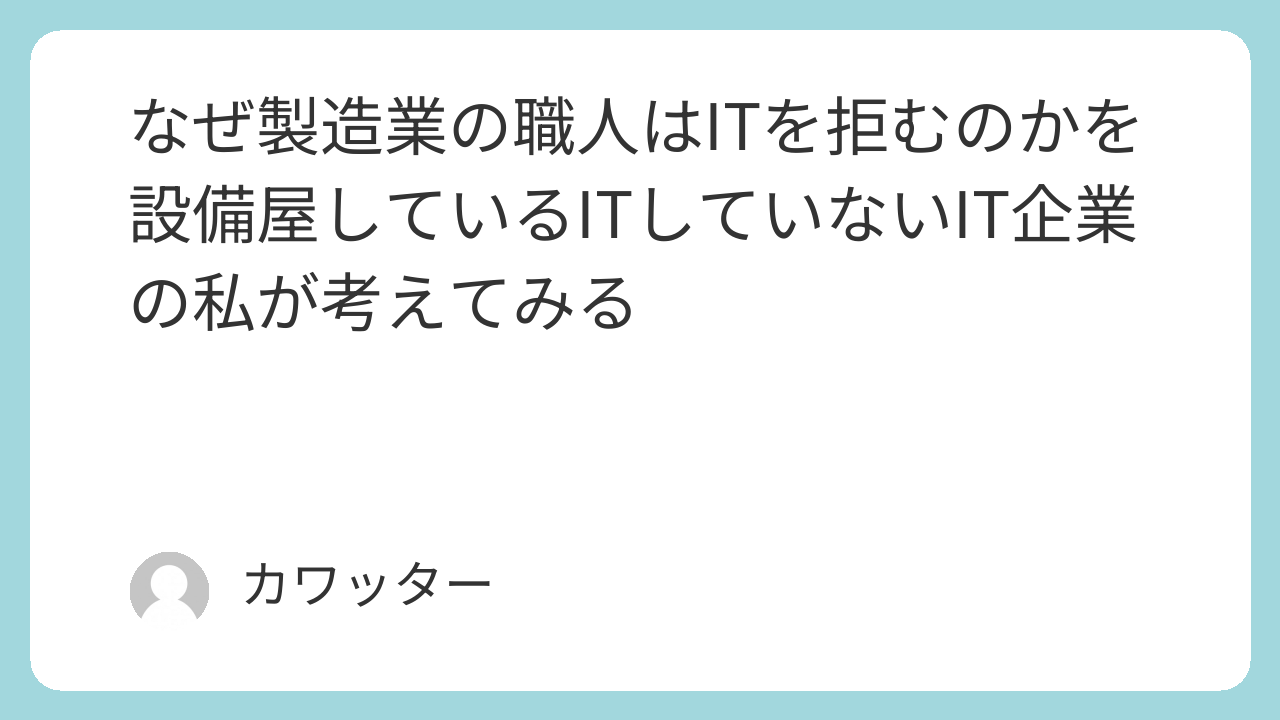
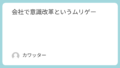
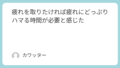
コメント スパム対応をしたつもり、コメントは残す方向で頑張ってます